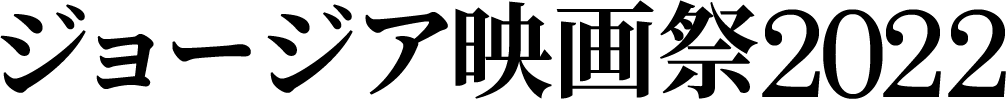コーカサスからの風――
[主催] ジョージア映画祭2022実行委員会
企画:はらだたけひで/企画協力・日本語字幕:児島康宏/上映素材制作:大谷和之
[共催] 一般社団法人コミュニティシネマセンター
[協力] ジョージア国立フィルムセンター、ジョージア国立アーカイブ、ジョージア・フィルム、ジョージア映画発展基金、ジョージア映画アカデミー
[後援] 在日ジョージア大使館
[上映・巡回に関するお問い合わせ]
コミュニティシネマセンター
Tel:050-3535-1573 Email:film@jc3.jp
2月26日、岩波ホールほか全国順次公開 公式サイト
巡回情報
| エリア | 会場名 | 日程 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 岩波ホール | 2022年1月29日(土)~2月25日(金) | チラシ |
| 群馬・高崎 | 高崎映画祭 | 2022年3月25日(金), 26日(土)、30日(水)、31日(木) | 上映作品 |
| 京都 | 京都みなみ会館 | 2022年4月15日(金)~5月5日(木) | チラシ |
| 神奈川・横浜 | 横浜シネマリン | 2022年5月7日(土)~27日(金) | チラシ |
| 大阪 | 大阪シネ・ヌーヴォ | 2022年5月28日(土)~6月24日(金) | チラシ |
| 広島 | 広島市映像文化ライブラリー | 2022年6月22日(水)~7月10日(日) | チラシ |
| 名古屋 | 名古屋シネマテーク | 2022年9月10日(土)~22日(木) | チラシ |
| 広島 | 広島市映像文化ライブラリー | 2022年9月23日(金)~25日(日) *祈り三部作のみ上映 | チラシ |
| 岡山・真庭 | 真庭中央図書館 | 2022年11月18日(金)~20日(日) | チラシ |
| 大分 | 大分シネマ5 | 2022年11月26日(土)~12月9日(金) | チラシ |
| 川崎 | 川崎市アートセンター | 2022年12月24日(土)~12月28日(水) | チラシ |
作品紹介
・「祈り」(シネスコ)、「大いなる緑の谷」「井戸」「喜びの家」「ケトとコテを求めて」「幸福」(ヴィスタ)、これら以外はスタンダードサイズ ・「少女デドゥナ」は原版が劣化しているため鑑賞条件は劣ります。
解説:はらだたけひで ©T.Harada
-
 【 Aプログラム 】シェンゲラヤ家の栄光『エリソ』
【 Aプログラム 】シェンゲラヤ家の栄光『エリソ』
1928年/監督:ニコロズ・シェンゲラヤ
『アラヴェルディの祭』
1962年/監督:ギオルギ・シェンゲラヤ
『白いキャラバン』
1963年/監督:エルダル・シェンゲラヤ
『青い山―本当らしくない本当の話』
1983年/監督:エルダル・シェンゲラヤ -
 【 Bプログラム 】放浪の画家ニコ・ピロスマニ特集『ピロスマニのアラベスク』
【 Bプログラム 】放浪の画家ニコ・ピロスマニ特集『ピロスマニのアラベスク』
1985年/監督:セルゲイ・パラジャーノフ
『ピロスマニ』
1969年/監督:ギオルギ・シェンゲラヤ
『ピロスマニ・ドキュメンタリー』
1990年/監督:ギオルギ・シェンゲラヤ -
 【 Cプログラム 】よみがえった歴史的名作『ハバルダ』
【 Cプログラム 】よみがえった歴史的名作『ハバルダ』
1931年/監督:ミヘイル・チアウレリ
『失楽園』
1937年/監督:ダヴィト・ロンデリ
『マグダナのロバ』
1955年/監督:テンギズ・アブラゼ、レヴァズ・チヘイゼ
『ナイロンのクリスマスツリー』
1985年/監督:レゾ・エサゼ -
 【 Dプログラム 】ミヘイル・コバヒゼ監督特集『結婚式』
【 Dプログラム 】ミヘイル・コバヒゼ監督特集『結婚式』
1964年/監督:ミヘイル・コバヒゼ
『傘』
1967年/監督:ミヘイル・コバヒゼ
『音楽家たち』
1969年/監督:ミヘイル・コバヒゼ
『井戸』
2020年/監督:エルダル・シェンゲラヤ -
 【 Eプログラム 】テンギズ・アブラゼ監督「祈り 三部作」『祈り』
【 Eプログラム 】テンギズ・アブラゼ監督「祈り 三部作」『祈り』
1967年/監督:テンギズ・アブラゼ
『希望の樹』
1976年/監督:テンギズ・アブラゼ
『懺悔』
1984年/監督:テンギズ・アブラゼ -
 【 Fプログラム 】第1回ジョージア映画祭アンコール『私のお祖母さん』
【 Fプログラム 】第1回ジョージア映画祭アンコール『私のお祖母さん』
1929年/監督:コンスタンティネ(コテ)・ミカベリゼ
『スヴァネティの塩』
1930年/監督:ミヘイル・カラトジシュヴィリ
『大いなる緑の谷』
1967年/監督:メラブ・ココチャシュヴィリ
『少女デドゥナ』
1985年/監督:ダヴィト・ジャネリゼ -
 【 Gプログラム 】オタル・イオセリアニ監督特集『落葉』
【 Gプログラム 】オタル・イオセリアニ監督特集『落葉』
1966年/監督:オタル・イオセリアニ
『歌うつぐみがおりました』
1970年/監督:オタル・イオセリアニ
『四月』
1962年/監督:オタル・イオセリアニ
『鋳鉄』
1964年/監督:オタル・イオセリアニ
『ジョージアの古い歌』
1969年/監督:オタル・イオセリアニ -
 【 Hプログラム 】国民的映画「ケトとコテ」を究める『ケトとコテ』
【 Hプログラム 】国民的映画「ケトとコテ」を究める『ケトとコテ』
1948年/監督:ヴァフタング・タブリアシュヴィリ、シャルヴァ・ゲデヴァニシュヴィリ
『喜びの家』
2008年/監督:メラブ・ココチャシュヴィリ
『「ケトとコテ」を求めて』
2009年/監督:ダヴィト・グジャビゼ -
 【 Iプログラム 】ゴゴベリゼ家・女性監督の系譜『ブバ』
【 Iプログラム 】ゴゴベリゼ家・女性監督の系譜『ブバ』
1930年/監督:ヌツァ・ゴゴベリゼ
『ウジュムリ』
1934年/監督:ヌツァ・ゴゴベリゼ
『インタビュアー』
1977年/監督:ラナ・ゴゴベリゼ
『幸福』
2009年/監督:サロメ・アレクシ
シェンゲラヤ家の栄光

エリソ
1864年、ロシア帝国は、コーカサスのチェチェン人(イスラム教徒)をトルコに強制移住させ、あとの土地にコサックを住まわせようとしていた。その計画を、チェチェン人のヴェルディ村の村長の娘エリソと彼女に恋するヘヴスリ人(キリスト教徒)のヴァジアが力を合わせて阻止しようとする。
シェンゲラヤ監督は、カズベギの原作を映画のために再解釈して脚色、村人たちの舞踊を要所にとり入れ、彼の得意とするリズム感ある構成に緻密なモンタージュを加えて映画化した。終盤、難民となった村人の女性が亡くなり、人々の沈んだ気持ちを鼓舞しようと、村長が始めた踊りが人々に歓喜とともに民族的エネルギーを呼び起こし、極限状況におかれた人々の魂が高揚してゆくシーンは出色である。その意味で、この作品は不屈なる民族的精神への頌歌ともいえる。
しかし1920年代の終わり頃、中央政府は社会主義リアリズムを提唱するなかで、モンタージュ等、アヴァンギャルドの手法を形式主義と批判し、「エリソ」は、彼の「26人のコミッサール」(1932)とともに批判され、長く上映禁止となった。

原作:アレクサンドレ・カズベギ 脚本:ニコロズ・シェンゲラヤ、セルゲイ・トレチャコフ 撮影:ヴラディメル・ケレセリゼ 美術:ディミトリ・シェヴァルドナゼ
出演:キラ・アンドロニカシュヴィリ(エリソ)、コフタ・カララシュヴィリ(ヴァジア)、アレクサンドレ・イメダシュヴィリ(アスタミル)、ツェツィリア・ツツナヴァ(ザズベカ)、イリア・マムポリア(セイドゥラ)

アラヴェルディの祭
東ジョージア、カヘティ地方にあるアラヴェルディ聖堂は11世紀に建立された由緒ある建築物。本作は、毎年秋に、ここで催される宗教的祭礼を舞台に、現代人に対して民族的伝統の真の意味を問う鮮烈な映像詩。原作は夭折した天才的作家グラム・ルチェウリシュヴィリ(1934~1960)である。
若いジャーナリスト、グラムは、アラヴェルディ聖堂で毎年行われる祭りの取材に向かう。そこで彼は人々が集まって酒を飲んで騒ぐばかりで、祭り本来の宗教的由来を忘れていることを知り、彼らに祭礼の真の精神を喚起させるために、ある大胆な行動を起こす…。
本作がギオルギ・S監督の僅か25歳の作であることに驚く。実際に祭に集まった一般群衆のなかでドラマを撮影するという手法は困難を極めたという。しかし完成した作品はダイナミズムに溢れ、しかも内省的な内容であり、映画中の主人公が荒馬を操るように制御されている。主人公の民族的意識の高まりと自問は印象的であり、後にギオルギ・S監督の代表作「ピロスマニ」(1969)へと結実してゆく。
スピード感ある撮影、モノクロームの斬新な映像美は一際心に残る。後年、監督として思索的な作風が高く評価されるアレクサンドレ・レフヴィアシュヴィリ(1938~2020)が担当。また乗馬シーンの演出も印象的だが、ギオルギ・S監督は映画大学時代にジョン・フォード監督作品など、アメリカの西部劇を好んで見ていたという。その嗜好は後の義賊を描いた「ハレバとゴギア」(1987)などの作品にも現れている。なお監督の話では、この作品は検閲でクレームがつき、最初の編集室のシーンは完成後に無理につけさせられたもので、このシーンを除いた版が自身の望む形だと語っていた。

原作:グラム・ルチェウリシュヴィリ(「20世紀ジョージア短篇集」未知谷刊) 脚本:レヴァズ・イナニシュヴィリ、ギオルギ・シェンゲラヤ 撮影:アレクサンドレ・レフヴィアシュヴィリ 美術:ゴギ・オチアウリ 音楽:フェリクス・グロンティ 他
出演:ゲイダル・パラヴァンディシュヴィリ(グラム)、コテ・ダウシュヴィリ、イラクリ・コクラシュヴィリ、レオ・バリセヴィッチ、ノダル・ピラニシュヴィリ、コンスタンティネ・トロライア 他

白いキャラバン
エルダル・S監督には、「奇妙な展覧会」(1968)、「奇人たち」(1974)、そして近年では「葡萄畑に帰ろう」(2017・原題「椅子」)など、ユーモアとアイロニーに富む寓話的な作品が多い。そのなかで本作は異色の社会派リアリズム作品である。2019年カンヌ国際映画祭カンヌクラシック部門で上映されるなど、近年ふたたび内外から高く評価されている。
コーカサスの険しい山岳地帯の村から、カスピ海沿岸へと羊の群れを追う牧夫たちの姿が描かれる。大昔からの彼らの生活――故郷の山村での生活は1年に僅か3カ月、毎年季節が来ると男たちは家族と別れ、羊の群れとの厳しい生活を送らなくてはならない。この生業は彼らの生まれた時からの定めなのか。映画は一人の若い牧夫の心の葛藤を通して、彼ら一人一人の思い――孤独、歓び、憧れ、切なさを見事に描き出す。また人々の様々な心理を、ジョージアを代表する個性派の俳優たちが見事に演じている。山から海へ、広大な大自然を背景にしたカメラワークも素晴らしい。エルダル・S監督のジョージアの伝統に生きる人たち、彼らの厳しい労働への尊敬がこめられ、切ない余韻を残しながらも民衆への共感と愛情が滲みでている作品である。

1963年/白黒/93分
脚本:メラブ・エリオジシュヴィリ 撮影:レオニド・カラシニコフ、ギオルギ・カラトジシュヴィリ 美術:クリステシア・レバニゼ、ディミトリ・タカイシュヴィリ 音楽:イラクリ・ゲジャゼ 他
出演:イメダ・カヒアニ(ゲラ)、アリアドナ・シェンゲラヤ(マリア)、スパルタク・バガシュヴィリ(マルティア)、ギオルギ・キカゼ(ヴァジア)、メラブ・エリオジシュヴィリ(バルタ)、ドド・アバシゼ(ドグヴィラ) 他
2019年カンヌ国際映画祭カンヌクラシック部門上映

青い山――本当らしくない本当の話
多くが屋内で撮影されるが、四季の変化を定点で映したトビリシの街角の表情がみずみずしい。真面目に働かずに個々の趣味や関心事に熱中して混乱を極める職員たち、その背後で持ち込まれた原稿が山積されている様が生々しく哀れである。この映画の狐につままれた、あるいは煙に巻かれた、ともいうべき奇妙な味わいは格別で、ジョージアの風刺コメディーの真骨頂だろう。登場する人物は個性的で愛すべき怠け者ばかりだが憎み切れない。独特な距離感が見る者に含み笑いをもたらす。ジョージア人にはとりわけ人気の高い作品である。
エルダル・S監督によれば、公開までには様々な困難が伴った。完成した作品をモスクワにもってゆくと、反ソ連的という理由で上映禁止を言いわたされた。しかしゴルバチョフがアブハジアへ保養にきたときに作品を見てもらうと、彼は大いに笑いながら「我々も国を建て直さなければ、この映画の建物のように崩壊してしまうだろう」と言って、最終的に公開許可を出したという。
この作品には、長年、ジョージア映画人同盟代表として、映画を製作する度にモスクワの当局へ御百度を踏まなければならなかったエルダル・S監督の苦い経験が背景にあるに違いない。

脚本:レゾ・チェイシュヴィリ 撮影:レヴァン・パアタシュヴィリ 美術:ボリス・ツハカイア 衣装:メデア・バクラゼ 音楽:ギヤ・カンチェリ 音声:ヴラディメル・ニコノフ 編集:T・アシアニ 他
出演:ラマズ・ギオルゴビアニ(ソソ)、テイムラズ・チルガゼ(所長)、ヴァジル・カフニアシュヴィリ(ヴァソ)、イヴァネ・サクヴァレリゼ(鉱山測量士)、セシリア・タカイシュヴィリ(経理係) 他
1984年全ソヴィエト映画祭グランプリ、2014年カンヌ国際映画祭カンヌクラシック部門上映
放浪の画家ニコ・ピロスマニ特集

ピロスマニのアラベスク
冒頭に「偉大なジョージア人画家の生涯と作品に捧げる」と記され、全体は大きく下記の九つの章に分けられている。①トビリシ②ソロラキ地区の写真家のアトリエ③歴史の1ページ/シャミール/エレクレ2世/タマルと詩人④動物⑤不毛と母性⑥宴⑦マルガリータへの花束⑧ニコのレクイエム⑨不滅への一歩。
ギオルギ・S監督の作品では、ピロスマニの黒い服装が印象的だが、この作品では最後の章で画家を黒から白い衣装に変えている。ピロスマニが絵で使う白の色は浄化を表すと考えられる。パラジャーノフ監督の映像とピロスマニの絵画は、モチーフの正面性、シンメトリーの構図、平面性というイコンに通じる共通点がある。映像ではその特性を充分に生かし、また木の切り株や黒い鳥など、ピロスマニの独特なモチーフもよく分析したうえで、全体を構成している。
長く沈黙を強いられてきたパラジャーノフ監督が、自らの感性を自由に解き放ち、宝石箱をひっくり返したような美的宇宙は、ピロスマニの質朴な世界とは一見異なるかもしれない。しかし両者は深層で通底しているのだろう。本作はピロスマニへの愛に満ち、パラジャーノフ監督の画家への誠実な思いが伝わってくる素晴らしいオマージュである。終盤のコラージュや、ピロスマニの絵で構築された小屋は、美術家としても知られるパラジャーノフの美術作品としても興味深い。

脚本:コリナ・ツェレテリ 撮影:ノダル・パリアシュヴィリ 音声:ガリ・クンツェフ 他

ピロスマニ
ジョージアは世界で二番目にキリスト教を国教に定めた国だ。冒頭のシーンで若きピロスマニが聖書を朗読する。そこで読まれるイエス・キリストがエルサレムに入城するくだりが暗示するように、ピロスマニの孤独な生涯がキリストの受難のように描かれてゆく。映画ではピロスマニの人生のエピソードが、時系列に、彼の絵を冒頭に据えた断片のように描かれるが、最後の「キリストの昇天」の絵が印象深い。また映像の随所に彼の絵のモチーフが実像化して置かれている。
脚本に6カ月、撮影に7カ月、全体で1年半を費やして製作された。台詞とシーンは極めて抑制され、よりミニマルな内容と構成にすることによって、映画は稀に見る純粋性、崇高な輝きを帯びている。撮影は、被写体の影を嫌い、曇天の日や午後の遅い時間を選んで少しずつ進められ、独特なトーンで全体が統一されている。もとよりピロスマニの絵はジョージアのイコンの伝統を受け継いでいる。映像も両者にならって正面性が重んじられ、平面的に描かれている。この映像的効果は大きい。またピロスマニを演じた画家アフタンディル・ヴァラジ(1926~1977)の存在なくして本作は語れない。
ギオルギ・S監督はモスクワ映画大学在学中に、エイゼンシュテイン監督の未亡人から、画家キリル・ズダネヴィッチが書いたピロスマニに関する本(1926)を贈られて関心を深めたと伝えられている。

脚本:エルロム・アフヴレディアニ、ギオルギ・シェンゲラヤ 脚本編集:レヴァズ・イナニシュヴィリ
撮影:コンスタンティン・アプリャチン、ドゥダル・マルギエフ、アレクサンドレ・レフヴィアシュヴィリ 美術:アフタンディル・ヴァラジ、ヴァシル・アラビゼ 音楽:ヴァフタング・クヒアニゼ、ノダル・ガブニア 他
出演:アフタンディル・ヴァラジ(ピロスマニ)、ダヴィト・アバシゼ(ヴァノ)、ズラブ・カピアニゼ(コラ)、テイムラズ・ベリゼ(ベゴ)、ボリス・ツィプリア(ディミトリ)、A・レフヴィアシュヴィリ(外国の美術家) 他
1974年シカゴ国際映画祭ゴールデン・ヒューゴ賞、アーゾロ国際映画祭最優秀伝記映画賞、
1973年英国映画協会サザーランド杯(2015年再映時は邦題を『放浪の画家ピロスマニ』に改題)

ピロスマニ・ドキュメンタリー
ギオルギ・シェンゲラヤ監督の息子、美術家のニコロズ・S氏が「ジョージアにはピロスマニを愛する人の数だけのピロスマニがいる」と語るように、彼の生前の記録は極めて少なく、彼が実際どういう人物で、どのような生涯を送ったのか未だに確かではない。本作は長年1862年とされていた生年への疑問、彼を発見した一人である詩人イリア・ズダネヴィッチとピカソとのエピソードなど、制作した時点で判明している情報が紹介されている。この映画の素材の由来は、ギオルギ・S監督が1990年頃の来日時に持参し、長年、はらだが預かっていたBETACAMを、遺族の承諾を得てDCP化したもので、現在はおそらく本国でも貴重な作品であることを記しておく。

脚本・ナレーション:ギオルギ・シェンゲラヤ 撮影:ザウル・サギナゼ 美術:ニコロズ・シェンゲラヤ 監修:メリ・カルベラシュヴィリ 編集:ギア・ヴァルジアシュヴィリ
よみがえった歴史的名作

ハバルダ
「ハバルダ」とは「道を空けろ」「どけ」という意味。本作の背景のひとつに、スターリンによる第一次五カ年計画(1928~1932)がある。1931年製作なので、社会主義経済を目指し、高い目標を掲げて重工業の発展、農業集団化が急ピッチで進められていた頃だ。しかし実際には抵抗もあり、多くの犠牲が払われたといわれている。題名が強烈である。しかし時代の狭間で揺れる製作者たちの葛藤が、作品に如実に現れている。表向きは五カ年計画のプロパガンダだが、政府側のメンバーはステレオタイプに描かれていて人間味がない。またこの計画を揶揄するような表現が多いことにも驚く。
ボルシェヴィキとメンシェヴィキの対立、ロシア紳士を大国主義者と罵り、ロシア紳士はジョージア野郎と侮蔑する二人の喧嘩、プロレタリア作家協会と芸術左翼戦線の争い、形式主義批判など、この時期の混乱がそのままに表されている。映画に登場する映画監督が「この歴史的事実を後世に残します」という通りである。当時批判の対象になったキュビズム風の絵やモンタージュも使用されている。
ソ連時代の映画資料には「教会を守ろうとする側の混乱をとおして、ロシア帝政におけるキリスト教社会の本質を批判的に描こうとした」と無難に書かれていた。酒場のシーンで歴史的伝統を祝う人たちは数年後、一人残らず粛清されただろう。見方によっては体制に辛辣な内容であり、チアウレリ監督が無事であったことが不思議に思われる。後にチアウレリ監督はスターリンに寵愛されるのだが。

脚本:S・トレチャコフ、ミヘイル・チアウレリ 撮影:アントン・ポリケヴィチ 美術:ラド・グディアシュヴィリ 助監督:Sh・ゲデヴァニシュヴィリ 監督補:A・ドゲブアゼ 統括:L・オガネゾフ 他
出演:S・ザリチェフ(ディオミド)、P・チコニア(ルアルサブ)、Sh・アサティアニ(労働者)、O・ヴァチナゼ(技術者)、N・ゴツィリゼ(詩人)他

失楽園
19世紀末、下級貴族にかわって裕福な農民が田舎の権力者となり、誰もが富への競争に巻き込まれ、貴族は没落していったという。そのような社会的背景で描かれたといわれるが、映画は温かいユーモアにあふれている。悪人さえも寛容に受け入れ、その思いを観客も共有するというジョージアのコメディー映画。ソ連体制下でも、彼らを真から批判的に描くことはない。
貴族兄弟の傾いだ家、壊れたままの門、一足しかない靴の取り合いなど、笑いを誘う行き届いた演出、物語を盛り上げる伏線がいくつもあって飽きさせない。ソヴィエト的イデオロギーはお飾りのように感じ、ジョージア民衆のエネルギーが、プロパガンダや啓蒙的な主題を凌駕している。
しかし、製作は困難を極めた。撮影中、スターリンの側近ベリヤから、突然撮影の停止命令が届き、その後の2カ月間、製作関係者は現場で粛清の恐怖に怯えて過ごしたという。そしてある日、幸いに再開の許可が下りたが、その時には彼らの気力や想像力は完全に打ち砕かれていた。当時、ロンデリ監督の周囲の人たちはみな粛清され、彼は階段の足音にも全身が凍りつく日々を送っていた。ある日、ベリヤに呼び出された際には死を覚悟し、家族に別れを告げ、荷造りをして出かけたという。結局は待たされたあげくに、ベリヤは「ジョージアの貴族階級をあまりコケにしてはいけませんな。この国を救ったのは彼らなのです」と言い、彼の命は救われた。

脚本:ギオルギ・ムディヴァニ、ダヴィト・ロンデリ
撮影:ボリス・ブラヴリョフ 美術:ダヴィト・カカバゼ、クリステシア・レバニゼ 音楽:アンドリア・バランチヴァゼ 音声:ダヴィト・ロミゼ 他
出演:ドゥドゥハナ・ツェロゼ(ペペラ)、バトゥ・クラヴェイシュヴィリ(ラザリア)、アルカディ・ヒンティビゼ(ミケラ)、シャルヴァ・ベジュアシュヴィリ(アスラン)、シャルヴァ・ジャパリゼ(アンバコ)他

マグダナのロバ
ロシア帝政下、1895年のトビリシが舞台。欲深い商人に酷使されて病になり路傍に捨てられたロバを救った貧しい母マグダナと子どもたちの姿を通し、貧富の格差、権力や金のある者が社会を牛耳っていることの不公正さ、庶民の生活と情愛、子どもたちの純真な心を描いている。なによりも市井の人たちの目線で現実社会をリアルに厳しく捉えていることが、それまでの映画の傾向と異なり新鮮である。
19世紀の作家エカテリネ・ガバシュヴィリの小説を翻案した作品だが、監督たちによって大幅に手を加えられた。母子の努力で元気になったロバを見て、元の所有者である商人はマグダナにロバを返せと迫り、裁判沙汰になるが、原作ではロバは母子のものになってめでたく終わる。しかし、映画ではロバは商人に「奪われ」、社会の不条理が浮き彫りにされる。常套的な終わり方ではなく、見るものに現実的な衝撃を与えて問題提起をするという、お仕着せのヒューマニズムで終わらせなかった監督たちの気骨が感じられる。
1980年代末のジョージアの映画評論では、この結末の変更を、弱者が裁判に負けることによって、逆に人間の尊厳への擁護が鋭くなされ、作り手の現実認識を表現する新たな方法となったと書いてあった。しかし、このラストの改変は大きな議論になったらしい。映画の独自性を主張する監督たちの姿勢に対して、スターリン主義下の規範と大きく異なる語り口は、後に「スターリニズムの首枷に投げられた真の爆弾」とも評され、撮影所の上層部には「体制に批判的」と映り、彼らは身近な作家たちを動かして映画への批判を煽ったほか、製作の差し止めや監督の交代など、様々な圧力をスタッフに加えたという。


原作:エカテリネ・ガバシュヴィリ 脚本:カルロ・ゴゴゼ 撮影:レフ・スホフ、アレクサンドレ・ディグメロフ 音楽:アルチル・ケレセリゼ 美術:イオセブ・スンバタシュヴィリ 音声:ラピエル・ケゼリ 他
出演:ドゥドゥハナ・ツェロゼ(マグダナ)、リアナ・モイスツラピシュヴィリ(ソポ)、ミホ・ボラシュヴィリ(ミホ)、ナナ・チクヴィニゼ(カト)、アカキ・クヴァンタリアニ(ミトゥア)、A・オミアゼ(ギゴ爺さん)他
1956年カンヌ国際映画祭短編部門グランプリ

ナイロンのクリスマスツリー
一台の長距離バスに乗り合わせた様々な立場の老若男女を描き、群像劇を得意とするエサゼ監督の真骨頂ともいえる作品。ベテラン俳優が大勢出演しているが、見事に一般人化している。まさにジョージアのバイプレーヤーの競演である。
バスが出発するまでの人々の騒ぎ、道中での車内のいざこざを映したシンプルなロードムービーだが、緻密な演出が企てられていることがわかる。バスの乗客たちの無秩序な喧騒のなかにも哀愁があり、不思議に心に染み入る。当時のジョージアやソ連社会の混乱が反映されているのだろう。乗客たちがそれぞれに気持ちを率直に表し、ジョージア人らしく感情を奔出してぶつかり合い、それが最後にポリフォニーのハーモニーへと収斂されてゆく。大騒ぎの果てのラストシーンが胸にいつまでも残る。ここにはジョージア人としての誇りや願いが込められているのだろうか。個性的で魅力ある作品である。
エサゼ監督は多彩な才能の持ち主だったが、俳優として有名であり、本作にも数カットで出演している。また詩や絵画でも知られる。アブラゼ監督「懺悔」の冒頭、ケーキを頬張る小柄で小太りの男を演じたのがレゾ・エサゼである。
エサゼ監督追悼上映。遺族提供のBETACAMをDCP化して上映する。

脚本:レゾ・エサゼ、アミラン・ドリゼ 撮影・レヴァン・パアタシュヴィリ 美術:テムル・アルジェヴァニゼ 音楽:ビジナ・クヴェルナゼ 音声:ゲナディ・コルホヴォイ 衣装:L・パアタシュヴィリ 他
出演:ルシアン・ミカベリゼ、グラム・ペトリアシュヴィリ、ソフィコ・ゴルガゼ、コテ・チャントゥリシュヴィリ、ズラブ・キプシゼ、ダヴィト・ドヴァリシュヴィリ、シャルヴァ・ヘルヘウリゼ、ズラブ・カピアニゼ 他
1987年アヴェリノ国際映画祭ゴールデンカメラ賞
ミヘイル・コバヒゼ監督特集

ミヘイル・コバヒゼ監督の遺した作品は多くはない。しかし彼の詩的で斬新、自由な表現は、60年代のみならず、その後のジョージア映画の発展に多大な影響を与えたといわれる。
「結婚式」(1964)、「傘」(1967)、「音楽家たち」(1969)がよく知られていて、いずれも短篇で台詞がない。映像と音楽だけで表現した「純粋映画」とも評される。しかし難解ではなく、人間の悲喜劇を、ユーモア、ペーソス、アイロニーで織り込んだシネポエムともいうべき作品で、その軽やかで上質な味わいは世界的に高く評価された。フランスのアルベール・ラモリス監督やジャック・タチ監督に例えられたこともある。彼が亡くなった時にはジョージアの多くの映画人が悲しみに暮れた。

結婚式
脚本:ミヘイル・コバヒゼ 撮影:ニコロズ・スヒシュヴィリ 美術:ギヴィ・ギガウリ 音楽:ミヘイル・コバヒゼ 撮影助手:エリズバル・カカバゼ 音声:テンギズ・ナノバシュヴィリ 映像監督:イリア・コビゼ
出演:ギオルギ・カフタラゼ(青年)、ナナ・カフタラゼ(娘)、エカテリネ・ヴェルラシュヴィリ(母)、バアドゥル・ツラゼ
オーバーハウゼン国際短篇映画祭グランプリ

傘
傘はアルベール・ラモリス監督の描く赤い風船を想起させる。二人の心の機微を傘が生きているようにユーモラスに表現する。ジョージア人には傘をさす習慣はないようで、相合傘の図案もない。コバヒゼ監督は傘や列車に何をこめたのだろう、何も意味はないと一笑されるに違いない。シンプルなモチーフにもかかわらず映像は洒落た絵のようである。
同年製作のイオセリアニ監督「落葉」に主演したギオルゴビアニが、印象的な演技をしている。どちらが先の出演だったのだろう。
脚本:ミヘイル・コバヒゼ 撮影:ニコロズ・スヒシュヴィリ 美術:ギヴィ・ギガウリ 音声:テンギズ・ナノバシュヴィリ 音楽:ミヘイル・コバヒゼ 技術顧問:ゴギ・チヘイゼ 編集:ヌグザル・アマシュケリ
出演:ジャナ・ペトライティテ(娘)、ギア・アヴァリシュヴィリ、ラマズ・ギオルゴビアニ、バアドゥル・ツラゼ
クラクフ国際短篇映画祭グランプリ

音楽家たち
二人の男のユーモラスなパントマイム劇が展開される。その一人はコバヒゼ監督が演じている。男が一人でチェスをしていると、行進曲が聴こえてくる。男が双眼鏡で遠くを見ると、向こうからも男が望遠鏡で見ている。二人は駆け寄って友情を確かめ合い、ダンスをする。そして、追いかけっこ、フェンシング、かくれんぼ、闘牛ごっこ、実際に牛がやってきて遁走、挙句の果てに銃や大砲、騎馬も出てきて、一人は倒れる。遠くからヴァイオリンが聴こえてきて、コントラバスとの合奏になり、再び最初の出会いに戻り、仲直りのダンスでおしまい。二人の遊び戯れる姿は人間関係の様々な局面を表しているのか。
センスに溢れた素敵な短篇である。上映禁止になった理由はわからない。当時のジョージアの撮影所長ロマノフは、「音楽家たち」を上映禁止にするだけではなく、コバヒゼ監督の映画製作まで禁止してしまう。コバヒゼ監督は抗議をこめて映画製作から離れ、アニメーションのシナリオ執筆や、建設関係の職人となった。木片をモザイク状に組み合わせた緻密な床作りが評判だったともいわれる。
ある識者によれば、「音楽家たち」を上映禁止にしたのは、ジョージアではなくモスクワからの命令であり、ロマノフは逆らうことはできなかったという。それではモスクワがなぜ禁じたのか、上映禁止の権限を握るのはロマノフだったが、コバヒゼ監督と関係が悪かった何者かが妬みで密告し、ロマノフに無理やり決定させたのではないかともいわれる。
脚本:ミヘイル・コバヒゼ 撮影:アベサロム・マイスラゼ、アレクサンドル・アンティペンコ 音楽・振付:ミヘイル・コバヒゼ 音声:テンギズ・ナノバシュヴィリ 監督助手:R・コルザイア、Ts・ナカシゼ、M・エリスタヴィ 撮影助手:L・マチャイゼ、Z・グダヴァゼ、G・クレリ 編集:N・アマシュケリ 映像監督:S・シハルリゼ
出演:ミヘイル・コバヒゼ(ミシャ)、ギア・アヴァリシュヴィリ(ギア)

井戸

原作:レゾ・チェイシュヴィリ 脚本:アミラン・ドリゼ、エルダル・シェンゲラヤ、ルスダン・ピルヴェリ 撮影監督:グリ・ゴリアゼ 美術:タマズ・ボチョイゼ 音声:パアタ・ゴジアシュヴィリ 協力:ルスダン・ピルヴェリ
出演:パアタ・モイスツラピシュヴィリ、ニネリ・チャンクヴェタゼ、ギオルギ・グルグリア、ヴァシコ・オディシュヴィリ他
テンギズ・アブラゼ監督
「祈り 三部作」


祈り
撮影は、辺境ともいえるシャティリの石造りの村を中心に行われた。モノクロームの荘厳な映像が鮮烈である。撮影はウクライナのアレクサンドレ・アンティペンコ。白と黒の対立は光と闇、善と悪を思わせ、登場人物の表情は旧約聖書のように厳めしく、劇的な物語の展開が宗教劇のように見るものに迫ってくる。冒頭に、プシャヴェラの「人の美しい本性が滅びることはない」という言葉が置かれている。プシャヴェラの人間の善良さへの信頼に、アブラゼ監督の倫理性、審美性が融和し、魂の気高さや尊厳が明確に表わされている。この言葉は「祈り 三部作」に共通する普遍的なテーマでもある。愛、友愛、寛容という人間の理想を象徴している。また原作にはないシーンが断続的に挿入される。白い装束の聖女、彼女を陵辱する悪魔のような男、ヘヴスリの戦士による3人の象徴劇である。人間の内面的な葛藤を描き、最後の聖女の処刑によって悪が勝利するようにも思えるが、一縷の希望を残す。
原作:ヴァジャ・プシャヴェラ(冨山房インターナショナル刊) 脚本:アンゾル・サルクヴァゼ、レヴァズ・クヴェセラヴァ、テンギズ・アブラゼ 撮影:アレクサンドレ・アンティペンコ 美術:レヴァズ・ミルザシュヴィリ 音楽:ノダル・ガブニア 音声:ミヘイル・ニジャラゼ 編集:ルシア・ヴァルティキアニ 他
出演:スパルタク・バガシュヴィリ(グヴティシア)、ルスダン・キクナゼ(白い衣の女性)、ラマズ・チヒクヴァゼ(マツィリ)、テンギズ・アルチヴァゼ(アルダ)、オタル・メグヴィネトゥフツェシ(ジョコラ)他
1973年サンレモ国際映画祭グランプリ

希望の樹
原作は作家ギオルギ・レオニゼ(1899~1966)が1962年に発表した21編の短編集。レオニゼの幼年時代の思い出、詩的なイメージやファンタジーが渾然とした内容であり、作家から原作を贈られて以来、アブラゼ監督はこの多元的で詩情豊かな世界の映画化を夢見ていた。因習の中に生きる長老ツィツィコレ、過去の栄光に固執する学者ブンブラ、新しい時代を待ち望むアナーキストのイオラム、奇跡を求める夢想家エリオズ、想像の恋に生きる女プパラ、欲望を捨てられない神父オフロヒネ、村中に色気をふりまくナルギザ‥。彼らを演じるジョージアの名優たち、リカ・カヴジャラゼ、ソフィコ・チアウレリ、セシリア・タカイシュヴィリ、カヒ・カフサゼ。ラマズ・チヒクヴァゼ‥。彼らの競演も素晴らしい。
ラストシーンのナレーションが心に残る。「ほこりとごみにまみれた所にこれほど美しい花が咲くとは。美しさはどこから来るのだろう。どこへ行くのか、どこへ消えるのか、しばし姿を隠すだけなのか」。アブラゼ監督は「人生において善良さと美しさを除いて、すべては過ぎゆくものだ」とも語っている。愚行が繰り返されても、アブラゼ監督は人間への信頼を決して失うことはない。
原作:ギオルギ・レオニゼ(「20世紀ジョージア短篇集」未知谷刊) 脚本:レヴァズ・イナニシュヴィリ、テンギズ・アブラゼ 撮影:ロメル・アフヴレディアニ 美術:レヴァズ・ミルザシュヴィリ 音楽:ビジナ(アレクサンドレ)・クヴェルナゼ、ヤコブ・ボボヒゼ 録音:テンギズ・ナノバシュヴィリ 編集:グルナラ・オミアゼ 他
出演:リカ・カヴジャラゼ(マリタ)、ソソ・ジャチヴリアニ(ゲディア)、ザザ・コレリシュヴィリ(シェテ)、コテ・ダウシュヴィリ(ツィツィコレ)、ソフィコ・チアウレリ(プパラ)、カヒ・カフサゼ(イオラム)、ラマズ・チヒクヴァゼ(オフロヒネ)、ギオルギ・ゲゲチコリ(チチコレ)、セシリア・タカイシュヴィリ(マラディア)他
1977年全ソヴィエト映画祭大賞、テヘラン国際映画祭金羊賞、審査員特別賞
1978年カルロヴィヴァリ国際映画祭特別賞、1979年ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞

懺悔
しかし、翌1985年に就任したゴルバチョフ書記長による改革、ペレストロイカ(建て直し)、グラスノスチ(自由な言論)が進められるなか、外務大臣に就任したジョージア出身のシェヴァルドナゼやジョージア映画人の強い働きかけによって、1986年10月にジョージアで公開され、翌87年1月のモスクワを皮切りに全ソヴィエトで公開されて、大きな反響を巻き起こした。
アブラゼ監督は「私たちは血なまぐさい方法で、長い間、善良さを根絶やしにしてきたことの報いを受けている。過去を葬った者は、現実に近づくことも、未来を見ることもできない。最大の罪は恐怖だ」と全体主義と順応主義の過ちを語っている。2008年の日本公開時に来日した主演のアフタンディル・マハラゼ氏もこう語っていた。「今公開されることはとても重要だ。でも残念なことがある。20年前に作られた作品を古く感じないということは、状況が変わっていないということだから」
監督:テンギズ・アブラゼ 脚本:ナナ・ジャネリゼ、テンギズ・アブラゼ、レヴァズ・クヴェセラワ 撮影:ミヘイル・アグラノヴィチ、ソロモン・シェンゲリア、ギア・ゲルサミア、ヴァレリ・シャヴェリ、グラム・サザグリシュヴィリ 美術:ギオルギ・ミケラゼ 音楽編集:ナナ・ジャネリゼ 録音:ディミトリ・ゲデヴァニシュヴィリ 他
出演:アフタンディル・マハラゼ(ヴェルラム・アラヴィゼ、アベル・アラヴィゼ)、イア・ニニゼ(グリコ)、メラブ・ニニゼ(トルニケ)、ゼイナブ・ボツヴァゼ(ケテヴァン・バラテリ)、ケテヴァン・アブラゼ(ニノ・バラテリ)、エディシェル・ギオルゴビアニ(サンドロ・バラテリ)、カヒ・カフサゼ(ミヘイル・コリシェリ)他
1987年カンヌ国際映画祭審査員特別賞、国際批評家連盟賞、キリスト教審査員賞
シカゴ国際映画祭審査員特別賞
1988年ソ連アカデミー賞作品賞、監督賞、主演男優賞、脚本賞、撮影賞、美術賞
第1回ジョージア映画祭アンコール

私のお祖母さん
次から次へと息つく間もなく新しい展開が用意され、特に人形のアニメーションを自由に使い、自殺を試みる主人公と興奮する妻と娘の異様なシーンは強烈である。破壊的なエネルギーに満ち、過激な内容だったために、ジョージア映画史上、初めて公開禁止になり、1967年までお蔵入りになっていた。ジョージアの人によれば、題名の「お祖母さん」は、「後ろ盾」を意味したという。
後年、当時の政府の記録を調べてみると「私のお祖母さん」公開禁止の理由は、「反ソ連的」さらに「当局に対するトロツキー的姿勢、ソヴィエト体制を腐敗させる」と書かれていた。当時の政治状況を考えると、ミカベリゼ監督は粛清されていてもおかしくなかったようである。

脚本:ギオルギ・ムディヴァニ、シコ・ドリゼ、コテ・ミカベリゼ
撮影:アントン・ポリケヴィチ、ウラディミル・ポズナン 美術:イラクリ・ガムレケリ 他
出演:アレクサンドレ・タカイシュヴィリ(官僚)、ベラ・チェルノワ(官僚の妻)、E.イヴァノフ(ドアマン)、アカキ・フォラヴァ(労働者)ミヘイル・アベサゼ、コンスタンティン・ラヴィツキ、シャルヴァ・フスキヴァゼ 他

スヴァネティの塩
1929年、カラトジシュヴィリ監督たちは、スヴァネティ地方で「盲者」という劇映画を作ったが、当局から形式主義だと厳しく批判され、お蔵入りどころか破棄されてしまう。しかし諦めきれないカラトジシュヴィリ監督は、編集段階で捨てたフィルムの断片を拾い集め、そこに個人的に撮っていた映像を加えて再編集し、ドキュメンタリー映画に仕立てあげた。それがこの「スヴァネティの塩」となり、今や映画史上の傑作と評価されるようになった。製作当時は、4~5回上映されただけで、当局によって上映禁止にされた。
カラトジシュヴィリ監督は、「軍靴のなかの釘」(1931)でも当局に批判され、20年もの間、製作の表舞台から消されてしまう。第2次世界大戦後、ようやく製作現場に戻った彼が、スターリンの死後に発表した「鶴は翔んでゆく(戦争と貞操)」(1957)は、見事カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞。スコセッシ監督やコッポラ監督に称賛された驚異的なカメラワークで見るものを圧倒するソ連とキューバの合作「怒りのキューバ」(1964)でも知られる。

脚本:セルゲイ・トレチャコフ
撮影:シャルヴァ・ゲゲラシュヴィリ、ミヘイル・カラトジシュヴィリ 美術:ダヴィト・カカバゼ 他

大いなる緑の谷
ソサナは、家族とともに「大いなる緑の谷」で、先祖から受け継いだ牛飼いを営み、牛とともに谷を転々としながら生活をしている。彼には土地の豊かな自然と、家族と、牛が人生のすべてであり、ほかの世界は想像できない。しかし妻のピリムゼは定住の生活を望んでいる。息子のイオタムは父を慕いながらも、両親の考えの違いを心配している。一方で、この地域では油田開発とともに新しい農村の建設が進み、自然環境も少しずつ変化し、現代文明はソサナの生活を脅かしてゆく。彼はこの変化に戸惑い、抗い、新しい時代は、土地の価値あるものを破壊することになると主張するが‥。
ジョージア人が先祖から受け継ぎ、誇りにしてきた土地と伝統ある生業を、体制が大義のもとに奪うことに対してココチャシュヴィリ監督は否を唱える。人々の悔恨と苦渋、怒りを主人公のソサナは一身に背負い闘う。全身で時代に体当たりするようなダヴィト(ドド)・アバシゼの力強い演技が印象深い。妻や息子などのキャスティングも素晴らしい。しかし、本作は10年間公開できなかった。社会主義の集団農場化、近代化に対して、個人の自由を尊重した、体制に対する大胆なアンチテーゼのためだろう。ドイツからの働きかけで、ようやく上映が許可されたという。
映画誕生100年を記念して催された1996年ペサロ国際映画祭で「世紀の100作品」に選定される。2017年、修復・デジタル化され、12月のトビリシ国際映画祭で披露された。

脚本:メラブ・エリオジシュヴィリ 撮影:ギオルギ・ゲルサミア 美術:ヴァシル・アラビゼ 音楽:ノダル・マミサシュヴィリ 音声:ラフィエル・ケゼリ 編集:ジュリエタ・ツォツォナヴァ
出演:ダヴィト・アバシゼ(ソサナ)、リア・カパナゼ(ピリムゼ)、ムジア・マグラヘリゼ(ソフィオ)、イリア・バカクリ(ギオルギ)、ズラブ・ツェラゼ(イオタム)、グラム・ゲゲシゼ、グリゴル・トカブラゼ
1968年エレヴァン国際映画祭監督賞、主演男優賞、撮影賞

少女デドゥナ
主演の少女マレヒ・リコケリは、ノダル・マナガゼ監督「春は去る」(1983)に出演していて「少女デドゥナ」は2作目。ジャネリゼ監督がロケハン中、東ジョージアのカンダウラという村で偶然彼女に出会い、その村で彼女を主演に撮影することにしたという。少年はテラビの寄宿学校で見つけ、ほかの登場人物はプロの俳優であり、監督はむしろプロの俳優の演技に気を使ったと語っていた。
原作は、イオセリアニ監督「田園詩」、アブラゼ監督「希望の樹」のレヴァズ・イナニシュヴィリの2、3枚の紙に収まるほどの同名の短篇である。当時、20代半ばだったジャネリゼ監督はこの作品に感銘を受け、親しかったイナニシュヴィリに声をかけてシナリオを書き始めた。
1985年マンハイム国際映画祭でグランプリを受賞する(ロシア語題名は「ほたる」)が、数本のプリントしか作られず、現在、本作のプリントはジョージアには存在しない。ネガはロシアが所蔵し、唯一のプリントはドイツのコレクターが所有している。今回の上映素材はジャネリゼ監督が個人的にもっていたDVD(おそらく状態の悪いプリントから制作したもの)からDCP化したものである。

原作・脚本:レヴァズ・イナニシュヴィリ 撮影:レリ・マチャイゼ 美術:ショタ・ゴゴラシュヴィリ、マルハズ・デカノイゼ 音楽:ヤコブ・ボボヒゼ 音響:イメリ・マンガラゼ
出演:マレヒ・リコケリ(デドゥナ)、ベシク・オドシャシュヴィリ、ザカリア・コレリシュヴィリ、タマル・スヒルトラゼ、レヴァン・ピルバニ、イリナ・グダゼ 特別出演:ジョージア国立弦楽四重奏団
1985年マンハイム国際映画祭グランプリ
オタル・イオセリアニ監督特集


落葉
ジョージア語の原題Giorgobistve は“聖ギオルギ祭の月”という意味であり、11月の古称である。様々なシーンから、ジョージア人の民族的な伝統、その精神性へのイオセリアニ監督の強い思いが伝わってくる。映画の冒頭と最後に映る古い教会は、トビリシ近郊にある6世紀のジュヴァリ聖堂。紀元前から5世紀頃まで、東ジョージアの首都だったムツヘタを見下ろす山の頂上にあり、ジョージアにキリスト教をもたらしたカッパドキア出身の聖ニノが十字架(ジョージア語でジュヴァリ)を建てた場所といわれ、人々の信仰の拠りどころの一つである。ソ連体制下で宗教表現はタブーであり、イオセリアニ監督は検閲の際には、教会のカットを大樹の映像に置き換えたと伝えられる。
冒頭のジョージア独特のワイン作りから、スプラ(ジョージア風宴会)までのドキュメンタリー風のシーンは印象的である。本作に要となるワインはジョージア人にとって魂の礎ともいうべきもので、人々の信仰と深く結びついている。この国はワイン発祥の地といわれ、8000年の歴史がある。クヴェヴリという土甕を使った伝統的な醸造法は、2013年にユネスコの無形文化遺産に登録されている。
本作には、ソ連体制主導の近代化、経済偏重、合理化に対して、ジョージアの伝統文化を守るという強い抵抗の思いが感じられる。ソ連邦の社会システムに対する痛烈な批判である。主人公ニコにイオセリアニ監督のその後の生き方が重なる。撮影はイオセリアニ監督「歌うつぐみがおりました」や「田園詩」も担当するアベサロム・マイスラゼ。
脚本:アミラン・チチナゼ
撮影:アベサロム・マイスラゼ 美術:ディミトリ・エリスタヴィ 音楽:ナテラ・イオセリアニ 音声:シャルヴァ・チティゼ、エヴゲニ・マッシ他
出演:ラマズ・ギオルゴビアニ(ニコ)、マリネ・カルツィヴァゼ(マリネ)、ギオルギ・ハラバゼ(オタル)、ドド・アバシゼ(レゾ)、アカキ・クヴァンタリアニ(ダヴィト)、アレクサンドレ・オミアゼ(工場長)他
1968年第1回ジョルジュ・サドゥール賞

歌うつぐみがおりました
彼は「現代病」に冒された「ジョージア人」なのか。忙しく楽しもうとするために苦しんでいるようにも見える。たびたび映る時計が、現代社会や人生の時間を思わせて暗示的。何よりもしばしばバッハのマタイ受難曲のアリア「神よ、憐れみたまえ」の旋律が流れることが印象に残る。
この作品もいくつかの解釈が可能だろう。「今をよく生きる。それもジョージア人らしく」はイオセリアニ監督作品に通底するテーマの一つでもある。本作は現代社会におけるジョージア人の生き方に問題提議をしているように思える。スプラもポリフォニーも出てくるが、ジョージアの伝統は今日の社会では本来の意味を失いつつあるとも。そしてギアは忙しい享楽の日々のなか、美しい女性に見とれるうちに交通事故にあってしまう。集まった大勢の群衆のなかに、彼の友人、知人もいるが誰も彼だとは気がつかず、一日が何事もなかったようにまた騒がしく始まる。
日常のなかに隠されている真実を、本作は明るみにする。人生において何が真実なのか。ギアが今日の社会で生命を謳歌する姿を描いて、生きる意味を観る者に考えさせ、人生の結末は、映画のように突然に訪れて、その儚さを考えさせられる。吹き抜ける風のような映画だが、脚本は緻密に構成され、人間と人生、そして社会を観察した冷徹な哲学であるにもかかわらず人間への愛情に満ちている。まさにイオセリアニ監督ならではの世界である。しかし現代社会への彼の視線は厳しい。この作品の後、「田園詩」と繋がってゆくことが理解できる。本作も2年間、公開を禁止された。
本作にはジョージアを代表するポリフォニーアンサンブル「ルスタヴィ」の代表、アンゾル・エルコマイシュヴィリ氏が客演している。彼は2021年3月、コロナのために急逝した。主演を演じたゲラ・カンデラキ氏は現在、映画製作会社の代表を務めている。
脚本:オタル・イオセリアニ、ディミトリ・エリスタヴィ、オタル・メフリシウィリ、シェルマザン・カキチャシュヴィリ 撮影:アベサロム・マイスラゼ 美術:ディミトリ・エリスタヴィ 音楽:テイムラズ・バクラゼ 他
出演:ゲラ・カンデラキ(ギア・アグラゼ)、ゴギ・チヘイゼ、イリネ・ジャンディエリ(リア)、ジャンスグ・カヒゼ(指揮者)、イリナ・ムディヴァニ、マリネ・カルツィヴァゼ、ヌグザル・エルコマイシュヴィリ 他

四月
冒頭にトビリシの旧市街の美しい街並みが映される。街角で人々は楽器を奏で、街はいつも歌に満ちている。これはイオセリアニ監督が思い描く理想世界だろう。この映画の主軸となる青年と娘の初々しい恋。一方で彼らのそばを行進する男たちは揃いの作業着を着て、郊外の近代的な団地の建設で忙しい。団地はどの部屋も表情のない四角い箱のよう。やがて街の住人は古い家を離れて団地で生活するようになる。どの家庭も以前とは異なり、それぞれの部屋で孤立した生活を送るようになる。
結ばれた二人もそこで生活を始めるが、何やら怪しい男から肘掛け椅子をもらったことを機に、家具が増え、電化製品などを買い集めることに熱中してゆく。そして物が増えると、次はドアの南京錠に熱中する。次第に彼らの関係が険悪になってゆく様を通して、物質文明を批判する。というより当時のソ連社会の風潮を批判しているのだろう。電気を使いすぎて停電になり、久しぶりに訪れた夜の静けさの中で吹かれるトランペットの調べが心に染みる。度々映される大樹の変容も象徴的である。
後半の夫婦喧嘩以外には一切台詞はない。この言葉も出鱈目らしい。冒頭から、古い街並みを幾何学的にとらえた映像、メルヘンのように男たちが楽器で奏でるプロローグの楽しさ。そして青年の激しい動き、特に靴の音に心を奪われる。その音がときどき楽器の音に変わる。生活音の緻密な構成に注意しながら作品を見ていると、イオセリアニ監督の本質はこの国の音楽、いくつもの音を束ねたポリフォニー(多声音楽)ではないかと思われ、映像さえもその一部に思えてくる。
脚本:エルロム・アフヴレディアニ、オタル・イオセリアニ 撮影:ユーリイ・フェドネフ 美術:エドゥアルド・ラプコフスキ 音楽:スルハン・ナシゼ 音声:V・マチャイゼ 特殊撮影:G・カスラゼ 他
出演:タティアナ・チャントゥリア(ムジア)、ギオルギ・チラカゼ(ヴァジャ)、アカキ・チクヴァイゼ、ヴェネラ・マイスラゼ、A・ジョルベナゼ 他

鋳鉄
冒頭に「ルスタヴィ冶金工場の溶鉱炉の工員たち、ショタ・ハレバシュヴィリ、レヴァズ・カンディアシュヴィリ、イリア・シンジハシュヴィリ、ダヴィト・ザマシュヴィリに、この映画を捧ぐ」とある。
撮影:Sh・シオシュヴィリ 製作:ジョージア科学教育・記録映画スタジオ

ジョージアの古い歌
(以下フランス語)「多声合唱の厳格な規則は、世代から世代へと今日まで受け継がれ、時代を経ても損なわれない洗練された声楽文化を形成している。ジョージアの各地方には多声合唱の独自の規則や流派がある。スヴァネティ、サメグレロ、グリア、カヘティ地方を訪ねよう」
ストラヴィンスキーはグリア地方の合唱曲「ハサンベグラ」を「人類が作った最高の音楽」と評し、ジョージアのポリフォニー(多声合唱)について、この国を代表する作曲家ギヤ・カンチェリは「ジョージアの音楽は独自の現象だ。――あるジョージアの三声の歌について、これはある日、バッハとベート-ヴェンとモーツァルトが出会い、三声の歌をうたおうと決めた結果生まれた作品ではないかと、しばしば想像したりしてる」(小林誠一訳)と語っている。
本作は、ジョージアの有名なポリフォニーを解説する映画ではない。スヴァネティ地方、サメグレロ地方、グリア地方、カヘティ地方の合唱風景の合間に、田舎の人たちの厳しい労働や風物が点描されている。合唱が人々の生活、労働、信仰と密接に結びついているということ、地方によって自然環境や暮らし、音楽までもが変わるこの国の多様さを伝えるドキュメンタリーである。ジョージア人の生活と音楽が密接であり、きめ細かなハーモニーを生んでいる様子が印象に残る。
撮影:T・チョホネリゼ 製作:ジョージア科学教育・記録映画スタジオ
国民的映画「ケトとコテ」を究める

ケトとコテ
19世紀半ば、ロシア帝政下のチフリス(トビリシ)。富裕な商人マカルは、美しい娘ケトを結婚させて、貴族階級に仲間入りすることを夢見ていた。そこでマカルは独身で破産寸前のレヴァン公爵に娘との縁談を働きかける。レヴァン公爵は商人とかかわることを望んでいなかったが、金のために結婚をやむなく受け入れた。しかしケトは公爵の甥の若い詩人コテと愛し合っていた。コテも事態を知って、結婚を仲介するハヌマに相談する。彼は絶望するケトのもとへゆき、2人は愛を確かめあう。ハヌマは若い2人を救うために驚くような策を考える‥。
昔のトビリシの街並みが、製作当時の技術を駆使し、実写と絵画を合成して見事に再現され、様々な階級の美男美女が出演し、明るく楽しく物語を展開してゆく。歌と踊りでドラマは流れるように進み、かつてのジョージアの風物詩、庶民の物売りキントや、商売人カラチョヘリなど、当時の風俗も華やかに再現されている。とくにラストシーンの舞踏会の踊りが見事。イリコ・スヒシュヴィリ率いる民族舞踊の名手たちの優美な舞いは息を呑むほどに素晴らしい。「終わりよければ、すべてよし」、上質なアメリカ・ハリウッドのエンタテインメントを彷彿とさせながらも、ジョージアの民族的伝統が満載である。しかし完成した映画はソ連当局の批判を受けて、教会の結婚シーンは削られ、1948年にジョージアで僅か2週間上映されただけで、スターリンの死の1953年まで、内外で上映されることはなかったという。


原作・脚本:セルゴ・パシャリシュヴィリ、ヴィクトル・ドリゼ(オペラ)、アフクセンティ・ツァガレリ(演劇)
撮影:アレクサンドレ・ディグメロフ 美術:イオセブ・スンバタシュヴィリ、パルナオズ・ラピアシュヴィリ 衣装:P.パリアシュヴィリ 音楽:ヴィクトル・ドリゼ、アルチル・ケレセリゼ 編集:ヴァシリ・ドレンコ
出演:メデア・ジャパリゼ(ケト)、バトゥ・クラヴェイシュヴィリ(コテ)、タマル・チャフチャヴァゼ(ハヌマ)、ペトレ・アミラナシュヴィリ(レヴァン公爵)、シャルヴァ・ガンバシゼ(マカル)、メリ・ダヴィタシュヴィリ(カバト)、ヴァソ・ゴジアシュヴィリ(シコ)、ギオルギ・シャヴグリゼ(ニコ)、ヴェリコ・アンジャパリゼ(女王)

喜びの家
19世紀後半、ジョージアでは演劇が大流行し、トビリシの人々は誰もがまるで舞台俳優のようだったという。そのトビリシという「喜びの家」なくして「ケトとコテ」の誕生はなかった。すなわち本作は映画の舞台である古き良きトビリシに捧げるオマージュでもある。映画の基となった戯曲「ハヌマ」は評判になり、ソ連時代を含めて全国90の都市で上演された。オペラや無声映画にもなり、「ハヌマ」は数十年の歳月をかけて映画「ケトとコテ」へと変容していったのだ。
当時、舞台演出家だったタブリアシュヴィリ監督は、撮影所所長だったミヘイル・チアウレリ監督に呼ばれ、「ケトとコテ」の映画化を提案されるが断る。書類にはスターリンのサインがあった。この案を断れば死か流刑を意味していた。しかし提案を受け入れた彼の心には一瞬にして作品の世界が拡がったという。「ケトとコテ」にはタブリアシュヴィリとゲデヴァニシュヴィリの両監督、撮影所所長チアウレリ監督が関り、その上にはスターリンという総監督がいたわけである。当時最高のスタッフ、キャストが結集し、数々の困難を乗り越えて映画は完成、絢爛豪華なミュージカル映画が誕生したが、当局によって上映禁止になる。本作はその政治的背景をさらに探求してゆく。

脚本:アカ・モルチラゼ 撮影:ギオルギ・ベリゼ 美術:コテ・ジャパリゼ、ギオルギ・タティシュヴィリ 音楽:ニカ・メマニシュヴィリ 音声:ヴァツラフ・フレグル 編集:レヴァン・クハシュヴィリ 製作:アルチル・ゲロヴァニ 出演:ラマズ・チヒクヴァゼ

「ケトとコテ」を求めて
「ケトとコテ」が製作された時代は、大戦後の窮乏していた時代。当時のスタッフは、寒いうえにパンもなく、いつもロビオ(煮豆)ばかりを食べていたという。そんな状況下で当時最高のスタッフキャストの力の源になったのは芸術への思いだった。60年後の「喜びの家」は、独立後の混乱でジョージア映画は死んだといわれた時代、経験豊かな映画人と新しく育った映画人がともに作った作品であり、ジョージア映画の蘇生を感じさせる。二つの時代の映画状況がいつしか重なってゆく。
「命のある限り、喜びの日々を祝え」という古代エジプトの言葉が象徴的に紹介される。「ケトとコテ」と、この映画を基に作られた2本のドキュメンタリー。これらは自ずとジョージア人の人生讃歌になっている。プロデューサー、アルチル・ゲロヴァニの「関係者はみな自由に動いてカオスのようだが、みな助け合って他の人の仕事も手伝う。カオスのなかで生まれるハーモニーが映画製作の秘訣だ」。「ケトとコテ」のタブリアシュヴィリ監督の「この世での生命を愛している」「愛は世界のあらゆる悪を滅ぼす魔法の力」など、印象に残る言葉も多い。

脚本・撮影・編集:ダヴィト・グジャビゼ 音声:ダヴィト・グジャビゼ、パアタ・グジャビゼ
ゴゴベリゼ家・女性監督の系譜- ラナ・ゴゴベリゼ監督「金の糸」公開記念 -

ジョージア映画の重鎮ラナ・ゴゴベリゼ監督はヌツァの娘にあたり、その娘サロメ・アレクシ監督はヌツァの孫にあたる。



ブバ
川の氾濫、土砂崩れなど、自然災害が絶えないなか、村人たちは日々、農作業に励む。貧困のために季節労働者として村を出てゆく男たち、彼らを見送る村人たちの群舞と川の濁流の映像を重ねたモンタージュが秀逸。さらに男たちの山仕事や木材運搬の重労働、激しい川下りの映像が力強い。一方で、家で母親の帰りを待つ揺りかごの幼子や、大人の仕事を手伝う健気な子どもたちの描写が心優しい。
水力発電所の建設により、重労働や貧困が解消されるというスターリンの五カ年計画のプロパガンダが名目のようだが、彼女が描こうとした主要なテーマは、コーカサスの厳しい大自然のなか、村人たちの四季折々の暮らしであり、ラチャ地方の民族的精神が鮮やかに描き出されている。
ヌツァ・ゴゴベリゼ監督
脚本:ヌツァ・ゴゴベリゼ 撮影:セルゲイ・ザボズラエフ 美術:ダヴィト・カカバゼ

ウジュムリ
西ジョージア、サメグレロ地方のリオニ川沿いの湿地帯が舞台。マラリアが蔓延する苛酷な環境を変えるために、水路を作る人々と古くからの土地の人々との軋轢を描いている。1930年代に主流だった新旧勢力の対立を描いた映画である。マラリアの感染を予感させる蚊や底なし沼を象徴的に使い、恐怖映画のように不吉な予感が漂う。ソヴィエトの新しい生活様式と伝統的な家父長制、家族制度が、「ブバ」に引き続き、彼女ならではの視点で描かれる。新しい生活を開拓する主人公たちが、呪術に頼る人々に勝利するが、蛙の女王ドドの怨念など、劇中で語られる土着の信仰が興味深い。児島康宏氏によれば、この地方にあった沼地には悪霊の伝説があり、ウジュムリとは悪霊の名前であり、西部の方言ではマラリアのことをウジュムリと呼んでいたという。
ギヤ・カンチェリの音楽がついた新版で上映する。
ヌツァ・ゴゴベリゼ監督
脚本:シャルヴァ・ダディアニ、ヌツァ・ゴゴベリゼ 撮影:シャルヴァ・アパキゼ 美術:ミヘイル・ゴツィリゼ 助手:D・アバシゼ、E・ガブリエリ 監督補佐:Z・グダヴァゼ
出演:コテ・ダウシュヴィリ(パルナ)、メラブ・チコヴァニ(カヴタル)、ヌツァ・チヘイゼ(マリアム)、イヴリタ・ジョルジャゼ(ツィル)、N・イアシュヴィリ(ゴチャ)、O・ゴゴベリゼ(イアグンディサ)他

インタビュアー
この映画にはゴゴベリゼ監督自身の忘れられない思い出が記されている。1937年、スターリンの粛清の時代、彼女が7歳のときに、才能ある映画監督だった母親ヌツァは、夫が粛清で処刑され、彼女も反政府の疑いをかけられて流刑となった。ラナが19歳のときにようやく母親と再会をはたす。その記憶がソフィコの思い出という形で再現されている。ソ連の歴史を知らなければ、彼女の脳裏に去来する、この映像の意味はわかりにくいだろう。検閲が厳しかった当時、この表現は冒険だっただろうが、多くの共感者がいたに違いない。ソフィコの娘はラナ監督の娘サロメが演じている。また取材を受ける女性の一人を「ロビンソナーダ」のナナ・ジョルジャゼ監督が演じている。
1977年/カラー/95分
脚本:ザイラ・アルセニシュヴィリ、エルロム・アフヴレディアニ、ラナ・ゴゴベリゼ 撮影・ヌグザル・エルコマイシュヴィリ 美術:クリステシア・レバニゼ 音楽:ギヤ・カンチェリ 音声:ウラディメル・ドリゼ
出演:ソフィコ・チアウレリ(ソフィコ)、ギア・バドリゼ(アルチル)、ケテヴァン・オラヘラシュヴィリ(ソフィコの母)、ジャンリ・ロラシュヴィリ(イラクリ)、サロメ(ヌツァ)・アレクシ=メスヒシュヴィリ(エカ)
1979年サンレモ国際映画祭グランプリ他

幸福
独立後の厳しい社会状況下、幼い子どもが三人いる家族の父親が交通事故で死亡する。妻はイタリアに出稼ぎに行き、一家に仕送りをしていた。彼女は不法移民のために葬儀に帰れず、携帯電話を通して夫の遺体に悲しみを切々と語り続ける。その言葉から、夫がどういう人物であったか、独立後のジョージアの社会状況の過酷さが見えてくる。そこに弔問者たちのそれぞれの思いが交錯し、奇妙な状況が生まれる。この国の社会状況を背景に、悲しくも可笑しい、ジョージアらしいユーモアとアイロニーに彩られた独特な含みのある作品である。
サロメ・アレクシ監督
脚本:ザイラ・アルセニシュヴィリ 撮影:ギオルギ・ベリゼ 音楽:ギヤ・カンチェリ 編集:ソフィオ・マチャイゼ 製作:サロメ・アレクシ、マリアム・カンデラキ
出演:ギア・アベサラシュヴィリ、ニカ・バヒア、ルスダン・ボルクヴァゼ、イア・スヒタシュヴィリ
「ジョージア映画祭2022」によせて
はらだたけひで(ジョージア映画祭主宰・画家)
わたしは1974年12月から2019年2月まで、およそ44年間、東京の岩波ホールで世界の映画を紹介する仕事に携わってきた。入社の日に突然映写技師を命じられ、それに反発し、辞表を出そうとして引き留められたことを懐かしく思い出す。電気関係が苦手だったわたしは映写機を扱う自信がなかったからだ。しかし、今にして映写を担当したことは貴重な経験だったと思う。「映画は20世紀の芸術だった」と過去形で語る方がいたが、わたしも近頃は、そうかもしれないと考える。映画は映画館の暗闇で見るものという基本的な考えは、コロナ禍のなかで急速に崩れている。プリント(フィルム)は、デジタル化が進んだ今日では見る機会さえない。わたしもご多分にもれずデジタルよりプリントの映像の方が遥かに好きだ。
岩波ホールとジョージア映画
この場では岩波ホールを定年退職後に、準備を重ねてきた「ジョージア映画祭2022」(2022年1月29日~2月25日、東京・岩波ホールにて、全国順次開催予定)について記したい。岩波ホールに在職中、わたしは56カ国、250本以上の映画の日本公開に関わったことになるが、なかでもとりわけジョージア(グルジア)の映画の紹介には積極的だった。『ピロスマニ』『落葉』『エリソ』『26人のコミッサール』『インタビュアー』『若き作曲家の旅』『青い山』『田園詩』『祈り』『希望の樹』『懺悔』『とうもろこしの島』『みかんの丘』『花咲くころ』『汽車はふたたび故郷へ』『皆さま、ごきげんよう』『葡萄畑に帰ろう』「ジョージア映画祭2018」、退職してからの『聖なる泉の少女』等、精一杯、情熱的に取り組んできた。
しかし、わたしには、仕事をやり残したという思いが拭えなかった。そしてそれを成し遂げることが、わたしの責務だと考えるようになった。それが「ジョージア映画祭2022」である。字幕翻訳のトビリシ在住の児島康宏さん、DCP素材制作の大谷和之さん、2018年の映画祭のときと同じメンバーで準備を進めている。
「ジョージア映画祭2022」では、ジョージアのソ連邦時代(1921~1991)の70年間における歴史的名作、全34本を一堂に集めて上映する。ジョージアというコーカサスの一国から20世紀の世界映画史を俯瞰するという試みである。いずれの作品も現在、本国ではスクリーンで見ることができない。また、これだけの規模の特集上映は世界的に見ても極めて稀である。しかし今や年金生活者である一個人がこの映画祭を開催できるのも、先ほど好まないと記したデジタル素材があるからこそ、なのである。
『ピロスマニ』公開の頃
1978年秋、わたしはジョージア映画『ピロスマニ』(日本海映画配給)の公開を担当した。ジョージアの孤高の画家ニコ・ピロスマニ(1862~1918)の半生を描いた作品である。岩波ホール入社前は信州あたりを転々と放浪し、独学で絵を描いていたわたしを、総支配人の故高野悦子が担当に相応しいと考えたのだろう。そしてわたしはこの映画に魅せられた。いや、魂を奪われたと表現したほうが正確である。画家の魂の純粋さ、絵を描くことへの矜持、映画の清冽な描写に強く魅せられた。当時はソ連邦の一共和国だったジョージアから来日したギオルギ・シェンゲラヤ監督は、ピロスマニに関心を深めるわたしに「ピロスマニを知るにはジョージアを知らなければならない」と語った。ピロスマニに限らず、この国の芸術の背景には、ジョージアという国の風土、民族、歴史や文化などのすべてが存在するという。この言葉から一本の映画には民族や作り手の熱い思いが込められていると知り、映画を公開するという仕事の責任の重さを痛感した。そして作り手たちの期待に応えたいとつよく思うようになった。わたしが24歳のときだった。

-723x1024.jpg)
シェンゲラヤ監督の言葉に応えるように、わたしは3年後の1981年6月、ソ連邦時代のジョージアをモスクワ経由で訪れた。当時は東西冷戦のさなかである。コーカサスの山々を越えての個人旅行は極めて少なかった。当時、岩波ホールは『ピロスマニ』の後、『家族の肖像』(1974/ルキーノ・ヴィスコンティ)『木靴の樹』(1978/エルマンノ・オルミ)『旅芸人の記録』(1975/テオ・アンゲロプロス)等が成功し、劇場としてようやく安定し、ミニシアター文化も拡がってきた頃で、スタッフは多忙を極めていた。わたしは渡航するために新婚旅行という名目で会社から休暇の許可を得たが、高野悦子はその企てを陰で笑っていたことだろう。
ジョージアではシェンゲラヤ監督と息子たちによって、東ジョージアのアラヴェルディ大聖堂、オープン間近の彼の亡き母、大女優ナト・ヴァチナゼのミュージアムや田園でのスプラ(ジョージア式酒宴)、ポリフォニー(多声合唱)等に連れていかれた。今、振り返れば、寝る間もないほどの過密なスケジュールだったが、ジョージア文化の精髄をわたしに教えるために周到なプランが練られていたと思う。帰国後、この国の民族文化に魅せられたわたしは、1986年に識者とともに「日本グルジア友の会」を立ち上げ、それから早くも36年が経つ。
-edited-scaled.jpg)

ジョージア文化と映画
2019年、日本を訪れたジョージアの大統領ズラビシュヴィリ氏は「ジョージアは戦争と芸術の国だったが、今は戦争がなくなり芸術の国になった」と端的に語っていた。確かにこの国の民族文化の背景には太古からの戦争の歳月があるようだ。この国はコーカサス山脈の南に位置し、東西南北の交易の要衝であり、3000年の歴史があるといわれる。例えば首都トビリシはアジアとヨーロッパ双方の影響を受け、ローマ神話の二つの顔をもつ「ヤヌスの顔」に例えられる。異国的なバルコニーのある建築物や石畳の街並みは旅人の眼には新鮮で美しい。
ジョージアは歴史的に周辺の国々、ペルシャ、モンゴル、トルコ、ロシア等から繰り返し侵略され、支配されてきた。しかし、人々は宗教(ジョージア正教)、言語(ジョージア語)、ワイン造り等、この国独自の文化を守り育み、またそれらを心の礎にして敵国と戦を交え、度重なる滅亡の危機から国を再生させてきた。
イオセリアーニ監督が、ジョージア人は一つの考えをもった集団になれないと語っていたが、この国の人々は個性を重んじる。その一方で、伝統的なスプラでは、タマダ(宴会の長)のもと、人々は魔法にかけられたように心を一つにする。スプラはただの宴会ではない。亡くなった人、祖先も共にいるという考えがあり、この世ならぬ時空が生まれる、わたしは宗教儀礼のように非日常の場と考えている。また、人が集まれば歌が生まれ、異なる歌声が束ねられて力強く美しいポリフォニー(多声合唱)となる。そして生活の根本には8000年の伝統があるワイン造りがある。葡萄の収穫とワイン造りは信仰と密接に繋がっている。また言語も文字も周辺の国々とは大きく異なり、その起源は未だに解明されていない。

映画館で働く者として、ピロスマニの絵から教えられたこともある。ピロスマニは黒いキャンバスに絵を描いた。描かれたモチーフは黒を背景に内から光を発するような効果を生む。これは映画館の暗闇でスクリーンに光を投影する映画の効果に似ている。白昼と暗闇では映像のもつ力に大きな差がある。映画館は非日常の世界を生む現代のアジールだった。

これらの独特な文化の背景には、大統領が語るように戦争の歳月があり、そこから生まれたジョージア人の人生観があると思われる。この国にはツティソペリ(一瞬のうちに過ぎるこの世の意味)という言葉がある。戦いはいつ起こるともかぎらず、戦いでいつ生命を落とすかわからない。苛酷な時代や運命に対して調和や平和を求め、はかないこの世に対して永遠の歓びを求めるジョージア人の夢が、この国の文化や風習に結実しているのではないか。ピロスマニが生前に語ったという、みなで芸術を語りあう「大きな木の家」の夢も根は同じである。
これらの個性的な民族文化は互いに緊密に関係しあい、今でもジョージアの人々の生活に不可欠のものだ。そしてジョージアの文化や風習は映画に最も集約されて表されていて、ジョージア映画の独特な個性を形作っている。言葉を変えるならば、ジョージア映画にはジョージア人の夢が込められているのだ。
ジョージア映画の魅力
ジョージア映画は人間描写だけではなく、独創性においても、欧米の映画とは一線を画する独特な味わいがある。巨匠フェリーニ監督は「ジョージア映画は奇妙な現象だ。特別であり、哲学的に軽妙で、洗練されていて、同時に子供のように純粋で無垢である」と語っていた。
ジョージアは、歴史的に大国に支配されても、その国の周縁に位置していたために、直接的な影響を免れて、独自の視座を維持することができた。自国の言語、宗教、文化を守ることができたことは大きい。またソ連邦時代にジョージア映画が個性的な世界を築くことができたのは、政治的、社会的抑圧のなか、人々の民族自決への強い願いが、その内容に影響を与えたことや、東西の冷戦下で、西側の商業主義から隔てられていたことなども理由にあげられるだろう。もとよりジョージアは19世紀から演劇が盛んであり、人々にはみな天性の表現者としての素質がある。地域性、民族としての素養、映画への愛、自由への渇望、ジョージア人であることの誇りが、自ずとフェリーニ監督の語る「奇妙な現象」を生み、発展させることができたのだ。
ジョージアで初めて映画が上映されたのは、パリでリュミエール兄弟が世界で初めて映画を上映した翌年、ロシア帝政下に置かれていた1896年である。ジョージアは1918年に独立するが、1921年2月、スターリンらが主導するボルシェヴィキ(赤軍)の侵攻によってソ連邦に編入されてゆく。その後のジョージア映画の70年間は、政治体制との闘いの日々でもあった。ソ連邦の体制下では、厳しい検閲によって、政府の意図にそぐわない映画は上映禁止になり、破棄された。関係者は粛清されて社会から排除された。しかしジョージアの映画人は、厳しい抑圧にも屈することなく、さまざまな表現方法を用いて果敢に映画を作り続けてきた。彼らは時代や運命に抗いながら、自身の道を切り開いてきたのだ。「ジョージア映画祭2022」の34本の上映作品中、およそ半数が上映禁止の憂き目にあっている。
かつて映画界の重鎮エルダル・シェンゲラヤ監督は「ジョージア映画はジョージアの人々のためのもの」と語っていた。ジョージア映画はこの国のポリフォニーのように多彩な豊かさを内包し、古代から伝わるワインのように芳醇である。そして伝統的な酒宴のように民族の魂を謳い、高揚させて、苦難のなかで人々の心を支えてきたのだ。

ジョージア映画祭2022
「ジョージア映画祭2022」では、「シェンゲラヤ家の栄光」「よみがえった歴史的名作」など、9つのプログラムに分けて、ソ連邦の激動する時代と人間を映した貴重な作品を揃えた。
1920年代のロシアアヴァンギャルドの影響を受けた芸術的意欲に富む作品。30年代の社会主義リアリズムが提唱され、スターリンによる粛清という暗黒の時代に作られた喜劇。40年代の世界大戦後の窮乏のなかで作られたミュージカル大作。50年代の雪どけの時代を予感させる新しい表現の作品。60年代の厳しい検閲にもかかわらず誕生した傑作の数々。70、80年代のソ連邦の解体を予感させる作品など。すでにご存じの「ピロスマニ」は最新のデジタルリマスター版を使用し、これまでで最良の版である。ほかにも「落葉」や「祈り 三部作」もあり、サイレントの傑作から、コメディー、社会派まで多彩な作品を日本語字幕入りで上映する。


70ページのパンフレットも用意している。ジョージア映画略史、34作品の解説資料のほか、2作品の映画原作の翻訳も所収する。また東ジョージアのパンキシ渓谷に住むキスト人の生活を追った日本のドキュメンタリー『祈りの谷』(2021/竹岡寛俊監督)もプレミア特別上映する。

これらの作品をとおして、映画の醍醐味を満喫していただきたい。そして20世紀の映画史を振り返るとともに、激動の時代を生きたジョージア映画人の愛や夢、情熱や勇気に思いを馳せていただきたい。ジョージア・フィルムのスローガンは「過去なくして未来はない」だった。
この映画祭の準備を進めながら、わたしはサイレント映画の豊かさを改めて実感した。俳優の個性、演技の素晴らしさに加え、動画で表現する喜びと興奮が伝わってくる。トーキー以降、映画は変化を続けているが、それがけっして「進化」ではないと思うようになった。
未知の作品にも注目していただきたい。『ハバルダ』(1931/ミヘイル・チアウレリ監督)は完成直後にお蔵入りになったと考えられ、スターリン時代の暗黒へと移行する時代の潮目を真正面から映し出している。監督が後にスターリンに寵愛されるチアウレリであることも興味深い。また戦後、スターリンの指示で作られたミュージカル『ケトとコテ』(1948)は今や国民的映画だが、当時は僅か2週間上映されて公開禁止になった。今回はこの作品に関する2本のドキュメンタリーも上映する。歴史の闇に光があてられ、製作の背景の知られざるドラマが語られる。


シェンゲラヤ家、チアウレリ家、ゴゴベリゼ家という映画における名門のことも記憶に留めていただきたい。戦後のジョージア映画の重鎮ラナ・ゴゴベリゼ監督は現在93歳。映画祭の終了直後から27年ぶりの新作『金の糸』(2019)が公開される。老いた女性作家をとおして人生と過去(ソ連時代)を捉えた知的で素晴らしい作品である。映画祭では、ラナの母、ジョージア最初の女性監督ヌツァ・ゴゴベリゼの幻の作品といわれた『ブバ』(1930)と『ウジュムリ』(1934)を紹介する。彼女は大粛清の年、1937年に流刑され、2作品は破棄されたと考えられていたが、数年前に発見されて復元された。


1991年4月、ジョージアは「再独立」し、12月にソ連邦は解体するが、ジョージアでは政府と反政府に分かれて内戦が勃発、同時に国内のアブハジア、南オセチアでも分離独立の紛争が激化し、多くの難民が生まれた。国全体が大きな打撃を受け、長期間にわたって映画製作も停滞した。またその間に、ジョージアにあったポジプリントの多くが、保管状況の悪化や2004年に起きたビル火災のために損傷した。ソ連時代にジョージアで製作された映画は、ジョージア・フィルムによれば、劇映画は1000本近く、ドキュメンタリーは2600本、アニメーションは350本といわれている。しかし現在、その多くはロシアのアーカイブの管理下におかれてジョージアにはない。その全容の調査そして返還が望まれるが、2008年に戦争が起こるなど、両国の関係が良好ではないことや、多額の費用が障害になっている。
21世紀に入り、ジョージアでは映画の関係機関が整備され、旧作品のデジタル修復など、厳しい財政のなかで少しずつだが再生に向けてさまざまな試みが行われている。この度の映画祭で上映するソ連時代の作品は、今日、デジタル上映が可能な映画のほぼすべてになる。

この僅か数年の間に、コロナ禍の影響もあったが、戦後から今日までジョージア映画を支えてきた映画関係者の訃報が相次いだ。ギオルギ・シェンゲラヤ監督、アレクサンドレ・レフヴィアシュヴィリ監督、ミヘイル・コバヒゼ監督、レゾ・エサゼ監督、ギオルギ・ダネリア監督、マルレン・フツィエフ監督、ザザ・ハルヴァシ監督、ザザ・ウルシャゼ監督、脚本家のレヴァズ・ガブリアゼ氏、俳優のカヒ・カフサゼ氏、作曲家のギヤ・カンチェリ氏、「ルスタヴィ」のアンゾル・エルコマイシュヴィリ氏。なんとたくさんの方々が逝ってしまったことか。ジョージア映画にとっては、かけがえのない人たちばかりである。特にG・シェンゲラヤ、ハルヴァシ、エルコマイシュヴィリの三氏は、ジョージアとの関りにおいてわたしにはかけがえのない方たちだった。もう彼らにお会いできないかと思うと辛くて残念でならない。わたしたち映画祭スタッフは「ジョージア映画祭2022」を、今は亡きジョージアの映画人、関係者に感謝をこめて捧げたいと思う。
はらだたけひで[原田健秀]
ジョージア映画祭主宰・画家。1954年東京生まれ。2019年2月まで44年間、岩波ホールに勤務する。1978年公開の『ピロスマニ』以降、同ホールでのジョージア映画公開に努め、2018年には創立50周年記念としてジョージア映画祭を企画する。絵本に『パシュラル先生』のシリーズ、『フランチェスコ』(ユニセフ=エズラ・ジャック・キーツ国際絵本画家最優秀賞)、『しろいおひげの人』など多数。著作に『グルジア映画への旅』、『放浪の画家ニコ・ピロスマニ』、『放浪の聖画家ピロスマニ』などがある。

ジョージア(グルジア)
Georgia=Sakartvelo